 真言密教のシンボルである、この根本大塔は弘法大師が高野山を開創され最初に着手した建物の1つで壇上伽藍(僧侶が修行をする閑静清浄な所)の中心に有り、朱色の高さ48.5m、23.5m四方で堂内中央には大日如来(胎蔵界)が祀られています。現在の大塔は昭和12年に再建された六代目ものです。
真言密教のシンボルである、この根本大塔は弘法大師が高野山を開創され最初に着手した建物の1つで壇上伽藍(僧侶が修行をする閑静清浄な所)の中心に有り、朱色の高さ48.5m、23.5m四方で堂内中央には大日如来(胎蔵界)が祀られています。現在の大塔は昭和12年に再建された六代目ものです。

大伽藍への入口は金剛峰寺の横に有るこの蛇腹路(じゃばらみち)から入ります。弘法大師が高野山の配置を龍に例え、このあたりが龍のお腹付近にあたる事から蛇腹道と呼ばれるように成ったそうです。この道を進むと最初に目に入るのが東塔です。昭和58年年に再建されました。


東塔の横には三昧堂(さんまいどう)が有ります。この堂は歌人西行が30年にわたり修行したところだそうです。このお堂の前には西行が植えた桜も有ります。
三昧堂の横には大会堂(だいえどう)が有ります。このお堂は鳥羽法王の皇女である五辻斎院(ごつじさいいん)内親王というお方が、父帝の追福のため建立されましたが当初はこの場所ではなく、後にここへ移築されました。


右の建物は愛染堂(あいぜんどう)です。このお堂は醍醐天皇の勅願により天下泰平を祈るために建立されました。現在も護摩祈祷を定期的にされているので何度か訪れた際に、祈祷されているお坊さんの後ろで手を合わせてお祈りしました。
 左手にある、この不動堂は高野山内で最も古く壇上伽藍内で唯一、国宝に指定されたお堂です。現在のお堂は14世紀初頭に再建されたもので明治41年この地に移築されました。このお堂は大変興味深く四隅の作りが全て違い4人の大工が四隅からてんでんバラバラに造ったと江戸時代から言われているそうです。
左手にある、この不動堂は高野山内で最も古く壇上伽藍内で唯一、国宝に指定されたお堂です。現在のお堂は14世紀初頭に再建されたもので明治41年この地に移築されました。このお堂は大変興味深く四隅の作りが全て違い4人の大工が四隅からてんでんバラバラに造ったと江戸時代から言われているそうです。

厨子の扉は硬く閉ざされ本尊である不動明王を拝観する事は出来ませんでしたが普段見られない内部を見る事が出来て満足でした。
不動堂の先に有る階段を上ると根本大塔があります。その反対側に大塔の鐘が有ります。
 この鐘は大師が発願され二世真然大徳の時代にようやく完成したと伝えられています。現在の鐘は1547年に完成したもので直径2.12mあり日本で四番目に大きな鐘であったことから高野四郎と呼ばれるようになりました。現在でも毎日午前4時、午後1時、午後5時(春季彼岸中日より秋季彼岸中日までは午後6時)、午後9時、午後11時の5回に分けて108の鐘の音を高野山内に響かせています。
この鐘は大師が発願され二世真然大徳の時代にようやく完成したと伝えられています。現在の鐘は1547年に完成したもので直径2.12mあり日本で四番目に大きな鐘であったことから高野四郎と呼ばれるようになりました。現在でも毎日午前4時、午後1時、午後5時(春季彼岸中日より秋季彼岸中日までは午後6時)、午後9時、午後11時の5回に分けて108の鐘の音を高野山内に響かせています。
 根本大塔と並んで弘法大師によって創建され壇上伽藍で重要な金堂が有ります。この堂は当初は講堂と呼ばれ高野山一山の総本堂で今でも主な行事はここで行なわれています。本尊は高村光雲作の薬師如来で、また曼荼羅の軸が掲げられてますが平清盛が自らの額を割った血で中尊を描かせた「血曼荼羅」と言われています。経年劣化による損傷が心配され先日、デジタル技術により複製の軸も作られたそうです。
根本大塔と並んで弘法大師によって創建され壇上伽藍で重要な金堂が有ります。この堂は当初は講堂と呼ばれ高野山一山の総本堂で今でも主な行事はここで行なわれています。本尊は高村光雲作の薬師如来で、また曼荼羅の軸が掲げられてますが平清盛が自らの額を割った血で中尊を描かせた「血曼荼羅」と言われています。経年劣化による損傷が心配され先日、デジタル技術により複製の軸も作られたそうです。
 金堂の裏手には弘法大師が唐より帰国する時に明洲の浜から真言密教を広めるに相応しい場所を探すために日本に向かって三鈷杵と呼ばれる法具を投げた所、紫雲が現れ雲に乗って飛んで行った。日本に帰国後、根本道場を建てるのに相応しい地を求め諸国を旅している時に白黒の2匹の犬を連れた狩人に出合い道場に相応しい地は無いか尋ねると犬に案内させると言って狩人はその場を立ち去った。
金堂の裏手には弘法大師が唐より帰国する時に明洲の浜から真言密教を広めるに相応しい場所を探すために日本に向かって三鈷杵と呼ばれる法具を投げた所、紫雲が現れ雲に乗って飛んで行った。日本に帰国後、根本道場を建てるのに相応しい地を求め諸国を旅している時に白黒の2匹の犬を連れた狩人に出合い道場に相応しい地は無いか尋ねると犬に案内させると言って狩人はその場を立ち去った。

途中、夜を明かすために神社に立ち寄ると、夢枕に女神が立ち、「あなたがこの山に来られたのは私の幸せです。この山を永久に献上します」と告げられた。そして犬に導かれるままに高野(たかの)を訪れたところ、唐の砂浜から投げた三鈷杵が松に引っ掛かっているのを見つけ、それにより、この地が真言密教を広めるに相応しい場所として決心したそうです。その言われからかこの松葉は3葉に成ってます。
ここを訪れた人達はこの松の下で3葉の松葉を拾ってます。私も拾ってお守り代わりに大切に財布に入れてます。

三鈷の松の前には御影堂(みえどう)が有ります。このお堂には、弘法大師が右手に三鈷杵、左手に数珠を持った有名な軸が祀られています。この軸は真如親王直筆の「弘法大師御影像」です。ここは高野山の重要な聖域の1つで有り限られた人しか堂内には入る事が出来ませんでしたが、近年に成って旧暦の3月21日(弘法大師が入定した特別な日)の前夜に行なわれる「旧正御影供」の時に外陣のみへの一般参拝が許されるように成りました。(写真の扉の内側をぐるりと廻って参拝出来ます。)当日、私も参拝しました。この日は伽藍内の殆どのお堂の正面扉が開放されていて祀られている仏様を拝む事が出来ます。(当然、、金堂などで秘仏と言われている仏様は見れません)根本大塔も正面扉が開けられ外から大日如来を拝むことが出来ます。
 御影堂の左横には准胝堂(じゅんていどう)が有ります。本尊の准胝観音様は弘法大師が得度の儀式を行う際の本尊として自ら造立されたと伝えられているそうです。現在のお堂は明治16年の再建です。
御影堂の左横には准胝堂(じゅんていどう)が有ります。本尊の准胝観音様は弘法大師が得度の儀式を行う際の本尊として自ら造立されたと伝えられているそうです。現在のお堂は明治16年の再建です。
写真の通り通常はどのお堂も正面の扉が閉ざされており正面の覗き窓から入る明かりでしか仏様を拝む事が出来ません。壇上伽藍で何時も堂内を拝観出来るのは根本大塔と金堂のみです。(有料ですが拝観する価値は十分有ります!)
 孔雀堂は干天(日照りで長く雨が降らないこと)の時に後鳥羽上皇の御願により東寺の延杲大僧正(えんごうだいそうじょう)が祈祷し、成就したことにより賞賜として建立されました。本尊の孔雀明王像は快慶作で重要文化財に指定され、霊宝館(高野山に関する沢山の国宝や文化財が収蔵されてます)に収められています。今では代わりの本尊が祀られていますが旧正御影供の時に拝観させて頂いた時の本尊は孔雀の背中に仏様が載っていました。
孔雀堂は干天(日照りで長く雨が降らないこと)の時に後鳥羽上皇の御願により東寺の延杲大僧正(えんごうだいそうじょう)が祈祷し、成就したことにより賞賜として建立されました。本尊の孔雀明王像は快慶作で重要文化財に指定され、霊宝館(高野山に関する沢山の国宝や文化財が収蔵されてます)に収められています。今では代わりの本尊が祀られていますが旧正御影供の時に拝観させて頂いた時の本尊は孔雀の背中に仏様が載っていました。

西塔は杉木立の中に建ち趣の有る佇まいを見せています。弘法大師はこの西塔を根本大塔と同様に密教世界の重要な建物として位置づけていました。大塔が胎蔵界大日如来に対して西塔は金剛界大日如来が祀られています。光孝天皇の勅命により高野山第二世である真然大徳によって建立されました。現在の塔は1834年に再建されてます。写真では分かりにくいですが石灯篭は江戸時代に世界で初めて全身麻酔を用いて乳癌手術を成功させた華岡青洲(和歌山県紀の川市)の寄進によるものです。開創1200年記念として今年、中門が再建されましたが、この木立の奥に有る樹齢数百年の檜が中門の再建に使われています。
 六角経蔵(ろっかくきょうぞう)、皇后の美福門院得子が後鳥羽上皇の菩提を弔うために創建しました。堂内には経が納められています。このお堂の前に立つと腰の辺りに把手が等間隔に何箇所か設置されており台座の部分が廻る様に成って一回りすれば一切経を一通り読誦した功徳が得るといわれているそうなので1人で挑戦しましたが全くビクともしませんでした。おじちゃん、オバちゃんの団体さんも挑戦してましたが廻りませんでした。日頃の功徳が足りんのかな~?
六角経蔵(ろっかくきょうぞう)、皇后の美福門院得子が後鳥羽上皇の菩提を弔うために創建しました。堂内には経が納められています。このお堂の前に立つと腰の辺りに把手が等間隔に何箇所か設置されており台座の部分が廻る様に成って一回りすれば一切経を一通り読誦した功徳が得るといわれているそうなので1人で挑戦しましたが全くビクともしませんでした。おじちゃん、オバちゃんの団体さんも挑戦してましたが廻りませんでした。日頃の功徳が足りんのかな~?
 山王院は御社(みやしろ)の拝殿として建立されました。山王院とは地主の神を山王として礼拝する場所の意味です。現在の堂は1845年に再建されたものです。
山王院は御社(みやしろ)の拝殿として建立されました。山王院とは地主の神を山王として礼拝する場所の意味です。現在の堂は1845年に再建されたものです。
御社は弘法大師が高野山開創にあたり丹生明神・高野明神を勧請しました。ここで言う丹生明神は三鈷の松で説明した女神で狩人は高野明神だったのです。また総社として十二王子・百二十伴神がまつられています。
 日本は古来より神を信仰する国でしたが平安時代には仏教が大きく信仰を集めた時代でした。平安時代には空海と一緒に唐に渡った最澄がいます。最澄は唐で天台宗を学び比叡山に延暦寺を建て修行の場としました。比叡山からは多くの開祖が誕生しています。浄土宗の法然上人、臨済宗の栄西禅師、浄土真宗の親鸞聖人、曹洞宗の道元禅師、日蓮宗の日蓮上人、時宋の一遍聖人、天台宗真盛派の真盛上人と多くの宗派が誕生した事から比叡山は仏教の母山と言われています。
日本は古来より神を信仰する国でしたが平安時代には仏教が大きく信仰を集めた時代でした。平安時代には空海と一緒に唐に渡った最澄がいます。最澄は唐で天台宗を学び比叡山に延暦寺を建て修行の場としました。比叡山からは多くの開祖が誕生しています。浄土宗の法然上人、臨済宗の栄西禅師、浄土真宗の親鸞聖人、曹洞宗の道元禅師、日蓮宗の日蓮上人、時宋の一遍聖人、天台宗真盛派の真盛上人と多くの宗派が誕生した事から比叡山は仏教の母山と言われています。
真言宗では人間は生きたまま仏に成れるとの教えがあります。空海は唐で密教(みっきょう=ひみつのおしえ)を学び高野山をひらきました。密教は、お祈りやおまじないによって望みをかなえたり、病気や災いを除いたり出来るといわれ、嵯峨天皇に子供が授からず空海の一番弟子である甥の智泉が祈祷を行い男子を授かった事から高野山を賜ったとの経緯もあります。高野山に一番最初に御社を建てた事からも空海は日本古来の神と仏教を崇め奉る神仏習合の思想も持っていたようです。













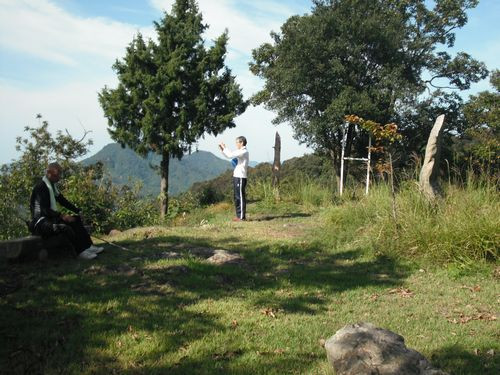


















































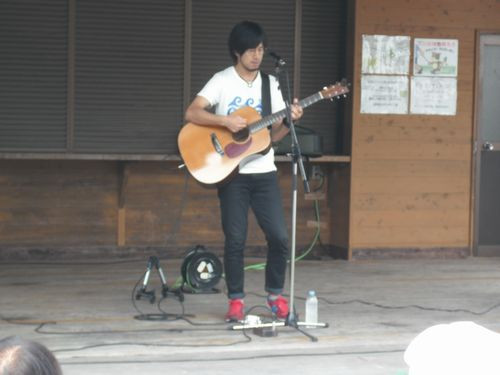

























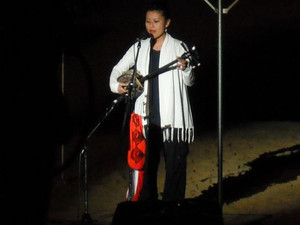
































































最近のコメント